目を上げて、私は山々を仰ぐ。わたしの助けはどこから来るのか。
詩編121篇1~2節
わたしの助けは来る 天地を造られた主のもとから。
この詩は「都上りの歌」と言われるもののなかのひとつです。都とはエルサレムのことで、なぜ都上りなのか、といいますと、エルサレムは海抜約800メートルの山の上にあるからです。多くのユダヤの民が巡礼の旅に訪れるときに、険しい道を必ず上ることになるのです。
この聖句を読むときに明治時代に生きた内村鑑三さん(以下、内村)に起きた出来事を思い起こします。内村が米国アマースト大学に神学を学ぶために留学していたときのことです。そのときの内村には悩みばかりでうつむいていました。「どうすれば善い人間になれるのか」、「どうすれば神学がわかるのか」。その大学の学長のシーリー先生はうつむいてばかりいる日本の青年に大層心配し、次のように言ったそうです。「内村、君は君の内のみを見るからよくない。君の外をみなければならない。なぜ己に省みることを止めて十字架の上に君の罪を贖い給いしイエスを仰ぎ見ないのか。」
そこで内村はぱっと悟り、ああ、そうだ、自分のことばかり考えても力が出ない。神様を見上げて神様に助けていただこうと思い、寄宿舎の屋上で祈ったときに転換したそうです。
日本に帰ってきた内村は、ひとりの文筆家、思想家として大活躍しました。内村は戦争に反対しました。しかし最初から戦争に反対していたわけではありません。日清戦争が終わるまでは義戦はあるのだと考えていたのです。しかしその考えに囚われ続けず、正しいと思ったことをペンで、言葉で、発信しました。
「日清戦争はその名は東洋平和のためでありました。しかるにこのこの戦争はさらなる大なる日露戦争を生みました。日露戦争もまたその名は東洋平和のためでありました。しかしこれまたさらに大なる東洋平和のための戦争を生むのであろうと思います。戦争は飽き足らざる野獣であります。」
内村の到達した考え方は、今日、戦争を知らない世代が多い日本のひとたちが知るべきことだと思います。
そして、内村が神に向き合うようになった心の境地は、まさに今月の聖句の詩編121篇のとおりだったと私は思います。
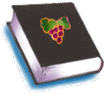



コメントを残す